| ◎ 住宅用火災警報器が鳴ったときは慌てずに ! |
| ○ まずは周囲を確認して慌てずに行動しましょう。 |
|
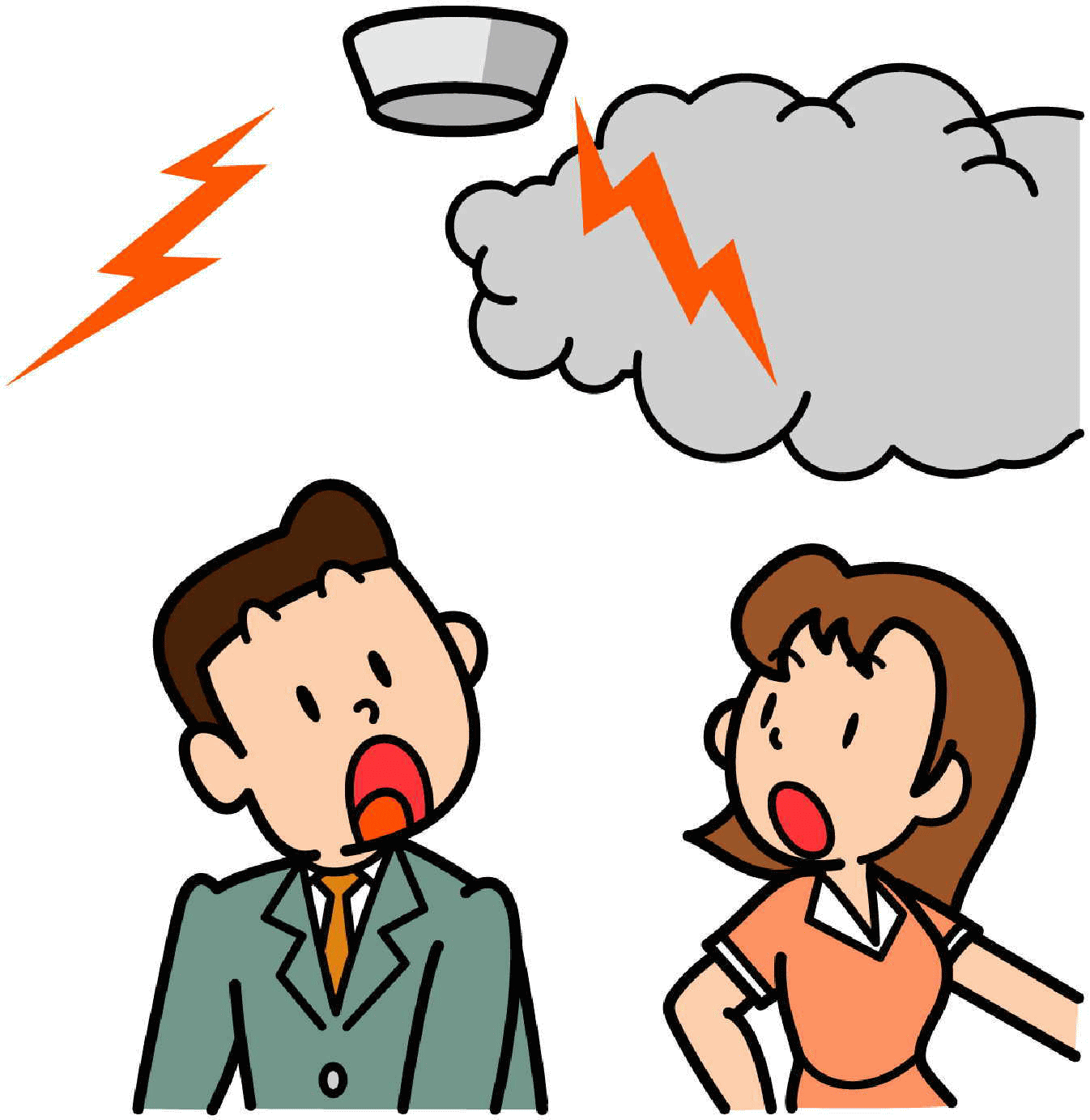 |
住宅用火災警報器が煙を感知すると、音声や警報音で火災の発生を知らせてくれます。
まずは周囲を確認して、慌てずに行動しましょう。 |
|
|
|
|
| ○ 火災のとき
|
- 火元を確認しましょう。
- 火災と確認したら、大声で周りに「火事だ!」と知らせ、すぐに119番通報してください。
- 「煙が少し出ている」「炎が少し見える」といった場合は消火器などで消してください。
- 「消火が無理」と感じたり、「危険」と思った場合はすぐに避難してください。
- 「煙が充満している」「炎が天井まで立ち上っている」というような場合も、すぐに避難してください。
|
| ○ 隣の家で警報器が鳴っていた場合は・・・・・・ |
- 煙や炎が出ていないか確認してください。
- 火災の場合は〈119番通報〉し、周囲に火災の発生を知らせてください。
- 初期消火、避難誘導、消防隊の誘導などにご協力をお願いします。
|
| ○ 火災ではないとき |
- 異常がないか周囲をもう一度確認しましょう。
- 火災以外でも、調理時に大量の煙や湯気が発生したときや、くん煙式の殺虫剤を使用したとき等には住宅用火災警報器が鳴ることがあります。頻繁に鳴る場合は、取り付け位置を変更してください。
- あやまって作動したことが確認できれば、ボタンを押すか、ヒモを引いて警報を止めます。その後、家族や近隣の人に火災でなかったことを知らせましょう。
|
| ○ 警報音の止め方 |
- 火災でないことを十分確認してから、警報器に付いている警報停止スイッチや、ひもを引くなどして警報音を止めることができます。
- 詳しくは、購入した際に付いている取扱説明書を確認してください。
|
| ○ 警報音が鳴った時にご活用ください。 →
|
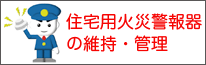 |
|
|
※ 住宅用火災警報器を取り付けた後には、住警器の設置効果を含めた定期的な維持・管理が必要です。
住宅用火災警報器は、電池が切れそうになった時や故障の際に音や光で知らせてくれる機種があります。
従って、警報器は電池切れや故障の時にも警報音が鳴る場合があります。
定期的に住宅用火災警報器の作動確認をし、警報音を聞きましょう。
警報音については、日本火災報知機工業会が製造会社別にまとめたホームページで確認することが出来ます。
また、住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。
火災警報器には、交換の時期があります。10年を目安に交換してください。 |
|
| ○お宅の火災警報器も、そろそろ10年。交換時期です。→ |
 |
|
|